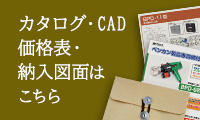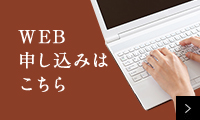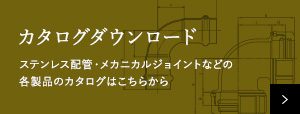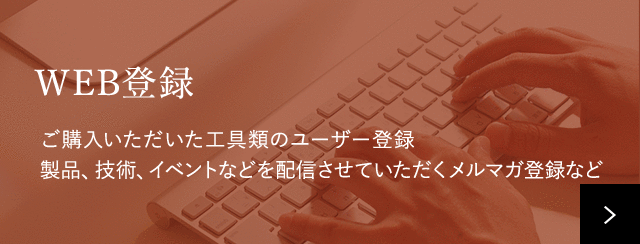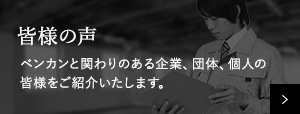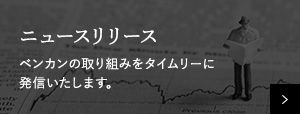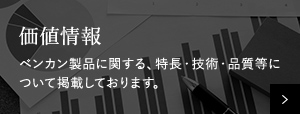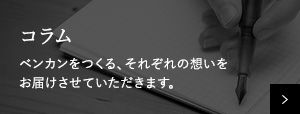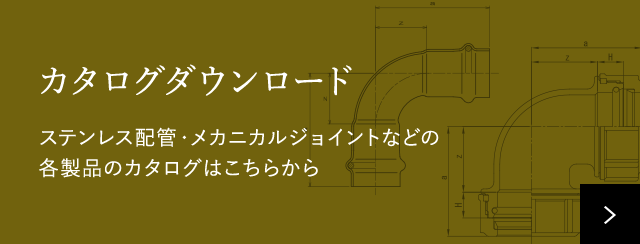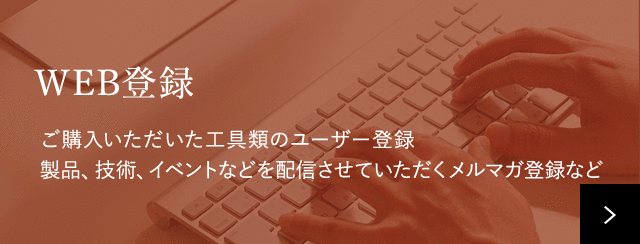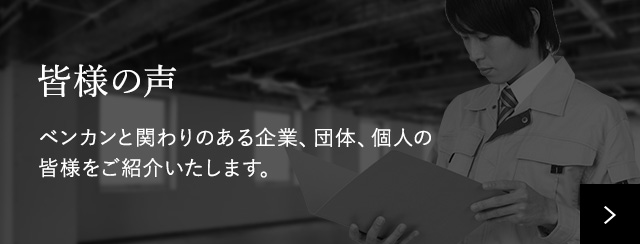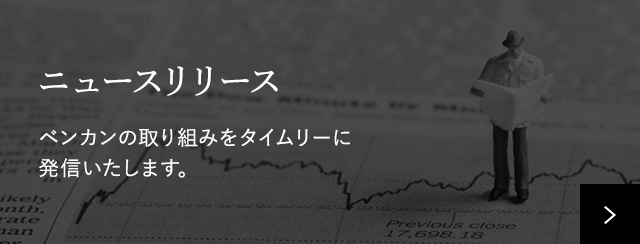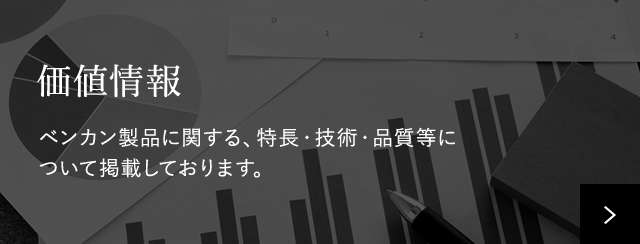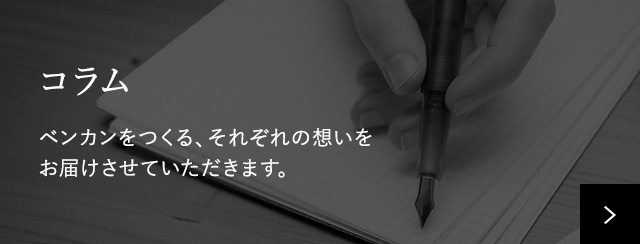ページが見つかりません
申し訳ありませんが、リクエストしていただいたページはこのサーバにございません。
次のような原因が考えられます。
- リンクに間違いがあるか、リンクが更新されている。
- URLが誤っている。
- ファイルが存在しない。
恐れ入りますが、トップページから再度ご訪問ください。
Page Not Found
The requested page was not found on this server.
It is possible that:
The link you followed has been broken, or the page has been renamed.
The URL you typed in may have been incorrect.
The page you are looking for has been removed.
Please return to the homepage, and try another link.